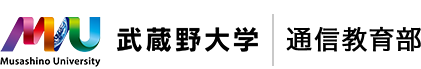武蔵野大学通信教育部
武蔵野大学大学院通信教育部 3つの教育方針
人間社会研究科 人間学専攻
学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)
仏教精神に則り学術の理論及び応用する能力を身につけていること。
現代社会の中で適応困難を来たしている人たちの心理や行動のメカニズムを理解する能力を身につけていること。
仏教の人間観、死生観に基づいて、社会の様々な課題を解決できる能力を身につけていること。
人間と社会環境に関して幅広く理解できる能力を身につけていること。
人間の精神、思考の根源の上に立って人間関係の新しい構築や修復を図れる能力を身につけていること。
教育課程編成方針(カリキュラム・ポリシー)
人間学専攻の教育課程は、生老病死の根源的問題について考察し、それを受容できる力と共感できる能力の修得を目的としている。そのために、1年次では、基礎となると「人間学系科目」の5科目を1年次の必修科目として履修させる。5科目の中、4科目については、学習方法として「レポート・スクーリング」も開講し、スクーリングにおいては、履修生によりグループワークや発表を行っている。2年次には選択科目として、これらの能力を応用するための「仏教・思想系科目」「心理系科目」「保健・福祉系科目」を重点的に研究させる。「人間学系科目」の「人間学特講」は2年次の全ての科目に、「死生学特講」は「仏教・思想系科目」に、「カウンセリング特論」と「グリーフケア特論」は「心理系科目」に、さらに「老年学特講」は「保健 ・福祉系科目」に関係し、基礎から応用という課程になっている。これらの科目は選択科目であるため、学習方法として「スクーリング」のみの科目も開講し、履修者による発表と教員によるコメント等も行っている。2年次ではさらに必修科目の「特定課題研究演習」によって、「人間性の危機に関する考察」「生と死をめぐる諸問題」「ライフサイクルとアイデンティティをめぐる諸問題」という課題の中から、それぞれの問題意識に基づく研究に取り組ませる。「仏教思想系科目」と「保健 ・福祉系科目」は「人間性の危機」と「生と死をめぐる諸問題」に関係し、「心理系科目」は「ライフサイクルとアイデンティティをめぐる諸問題」に関係している。「特定課題研究演習」は指導教員による個別指導で、より高い学習効果が生まれる。
人間と社会環境に関する幅広い理解を持ち、人間の精神、思考の根源の上に立って人間関係の新しい構築や修復を図れる人材を養成することを目的とする。
入学者の受入方針(アドミッション・ポリシー)
人間学専攻は、学位授与方針に記した内容を理解し、教育課程に積極的に取り組む姿勢を持ち、達成能力があり、自主的に時間管理ができ、社会に貢献する意欲を持った、以下のような社会人の学生を受け入れる。
- 人間性の危機に関心のある者
- 生と死をめぐる諸問題に関心のある者
- ライフサイクルとアイデンティティをめぐる諸問題に関心のある者
人間社会研究科 実践福祉学専攻
学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)
実践福祉学専攻では、実践力、研究力及び指導・管理能力に秀でた専門的な職業人および研究者・教育者養成の観点から以下の要件を満たした者に修士(社会福祉学)の学位を授与する。
- ソーシャルワークに関する研究力・実践力として、より高度な価値規範・倫理・知識に基づく判断やミクロ・メゾ・マクロレベル、国内外を視野に入れた実践・研究に従事する能力等を有していること。
- 多職種・機関との協働・連携、人材育成、組織運営管理、組織・社会の変革、資源開発、ネットワーキングに関する能力等を有していること。
- 3.科学的根拠に基づく研究・教育活動を行うための技術・知識等を有していること。
教育課程編成方針(カリキュラム・ポリシー)
実践福祉学専攻では、実践力、研究力及び指導・管理能力に秀でた専門的な職業人および研究者・教育者を養成することを目的としていることから、知識と実践の融合を可能とする循環型教育プログラム(具体的実践⇒知識の補完・修得⇒実践での施行⇒検証・評価⇒(再施行)⇒実践技能化・理論化⇒具体的実践)を志向し、それを可能とする教育課程を編成する。具体的には、原理科目群、実践理論科目群、関連領域科目群、リサーチ科目群により構成され、それぞれの科目群の特徴(科目配置の目的)は以下のとおりである。
- 原理科目群には、本学の理念に基づく科目及び実践福祉に関する原理、制度・政策に関する知識を習得する科目を配置する。
- 実践理論科目群には、ソーシャルワークの実践理論に関連して、基礎を理解する科目に加え、個人・家族、組織、コミュニティなど、ミクロ・メゾ・マクロレベルにわたる実践理論等を習得する科目を配置する。
- 関連領域科目群には、ソーシャルワークに関連する領域として、国内外におけるソーシャルワークの動向を学ぶことと、自らその動向をつかむ力を習得するための科目である「家族支援」「グリーフケア」「アントレプレナー」、「国際社会福祉」に関する科目を配置する。
- リサーチ科目群には、科学的根拠に基づく研究活動を行うための技術・知識として、リサーチに関する総論・各論、質的・量的研究法について習得する科目、当事者視点に立った社会福祉ニーズの抽出・分析のための調査・研究力を修得する科目を配置する。これらの学びをもとに、社会福祉学に関する研究を行い、修士論文もしくは特定課題研究論文を作成する。修士論文を執筆する場合には、「論文研究演習」にて、実践福祉学の個別分野に関する専門的内容の研究を計画し、研究指導、論文執筆指導を受け、論文を執筆する。特定課題研究を作成する場合には、「特定課題研究演習」にて、実践福祉学専攻の個別分野に関する専門的な内容の論文執筆指導を受け、作成する。
これらのカリキュラムにより、高度な専門知識・技術の習得と実践を循環させた教育プログラムにより、"人"と"社会"に対する深い洞察に基づく専門的倫理及びミクロ・メゾ・マクロレベルを視野に入れた高度な実践力を有し、指導・管理能力、研究力に秀でた専門的な職業人及び研究者・教育者を養成する。
入学者の受入方針(アドミッション・ポリシー)
実践福祉学専攻では、以下のような能力・意欲を有する者を求める。
- ソーシャルワーク専門職に求められる価値規範・倫理・理論等の理解を深め、より高度な実践力および研究力の修得を目指す者
- ソーシャルワーク専門職として、人材育成や組織・団体の管理運営に関するより高度な指導力・管理能力の修得を目指す者
- 社会福祉やソーシャルワークに関連する研究者・教育者、国内外の社会問題の解決、社会的起業を目指す者
仏教学研究科 仏教学専攻
学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)
仏教精神に則り学術の理論及び応用する能力を身につけていること。
仏教についての専門的知識を身につけていること。
仏教の人間観、死生観に基づいて、社会の様々な課題を解決できる能力を身につけていること。
人間と社会環境に関して幅広く理解できる能力を身につけていること。
人間の精神、思考の根源の上に立って人間関係の新しい構築や修復を図れる能力を身につけていること。
教育課程編成方針(カリキュラム・ポリシー)
仏教学専攻(修士課程)においては、建学の仏教精神に基づいて人間尊重の立場に立った研究活動を行い、仏教学に関する専門的な知識を修得し、実践力に優れた専門的な職業人もしくは研究者を養成するために必要な教育課程を編成する。この目的を達成するために、通信教育部の特性を活かし、授業形態としてレポート授業、ICTを活用した遠隔授業、及び、対面授業の三種の授業形態を用意し、学生の多様なニーズに対応する。
- 必修科目として「仏教学特論」と「仏教史特講」を置くことで(2020年度入学生~)、本研究科のすべての学びの基礎となる仏教学と仏教史について学修することができる。
- インド、中国、東南アジア、日本の思想・文化をそれぞれ学修する選択科目を複数設けることで、各自の関心にしたがった多様な学びが可能となっている。
- 「真宗概論」「真宗史」「真宗学特講」「浄土教理史」「真宗文献講読」「浄土教特講」などの選択科目を置くことで、本学と関わりの深い浄土真宗について総合的・体系的に学ぶことができる。
- 「現代仏教特殊研究」「近代仏教特講」「ターミナルケア特論」などの選択科目を置くことで、仏教精神に基づく社会実践活動について学ぶことができる。
- 必修科目の「特定課題研究演習」を履修することで、「仏教における人間観」「仏教史における諸問題」「現代社会の諸問題と仏教」のいずれかのテーマのもとに、指導教員の指導のもとに、主体的な文献研究を適切に行うことができる。
入学者の受入方針(アドミッション・ポリシー)
仏教学専攻は、学位授与方針に記した内容を理解し、教育課程に積極的に取り組む姿勢を持ち、達成能力があり、自主的に時間管理ができ、社会に貢献する意欲を持った、以下のような社会人の学生を受け入れる。
- 仏教における人間観に関心のある者
- 仏教史における諸問題に関心のある者
- 現代社会の諸問題と仏教に関心のある者
環境学研究科 環境マネジメント専攻
学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)
所定の40単位以上を修得し、以下の力が修得されたと認められ、特定課題研究の審査に合格した者に、修士(環境学)の学位を授与する。
- 自然の仕組みや持続可能な発展の概念を深く理解し、持続可能な社会に向かう自分なりの中長期的ビジョンを有している。
- 環境学についての幅広く深い知識や経験のもと、環境をめぐる解決や発展を図るため独自の問題意識を持てる。
- 以下いずれかの分野で専門性を実務に活かすことができる。
- 企業等における環境経営のための環境マネジメント推進者として、ESG経営などに関わる環境マネジメントシステムを理解し、システムの構築、実践、評価ができる。
- 企業活動や製造業におけるエコプロダクツ製品あるいは企業活動全体の環境評価推進者としてLCA手法等による評価ができる。
- 地域の低炭素化、循環経済、自然との共生など地域の持続可能な発展に貢献するため、地域社会の環境問題を発見、改善提案できる。
教育課程編成方針(カリキュラム・ポリシー)
環境学研究科では、環境に関する専門的職業人を養成するため、環境分野の社会動向を注視し、教育内容を時代に即して、持続可能な企業社会・地域社会の実現に対応できるカリキュラムを編成する。
具体的には、持続可能な発展の概念を深く学ぶ「持続可能な発展研究1」や環境問題の広がりや全体像を理解する「環境学演習」などを共通必修科目として配置し、それらをベースとして、「地域環境マネジメント」「環境経営」「エコプロダクツ」それぞれの領域について深く学べる科目群を配置する。学修方法としては、各科目の特性に応じて、レポート、スクーリング、及びそれらの併用のいずれかで行う。研究の集大成となる「特定課題研究演習」では、指導教員による継続的な論文指導を行う。
入学者の受入方針(アドミッション・ポリシー)
環境学研究科では、高度な知識と能力を発揮して、地域社会の環境マネジメント、環境経営、エコプロダクツの推進者、専門家又は研究者などとして、持続可能な社会における低炭素社会や循環型社会等の実現に貢献しようとする者を求める。
環境学同系統における学部教育で優秀な成績を修めた者、隣接異系統の学部教育で優秀な成績を修めた者、社会人として環境関係部署に関連した職務経験や相応の問題意識を有する者等を求める。
お問い合わせ
武蔵野大学大学院 通信教育事務課
TEL.042-468-3482
E-mail.dtsushin@musashino-u.ac.jp